FIRE(経済的自立・早期リタイア)を目指していると、必ずといっていいほど立ちはだかるのが「住宅ローン」という存在です。
家を買えば、20年~30年という長期の返済義務を負うことになる。それは一見、自由を求めるFIREの理念と真っ向から対立しているようにも見えます。
しかし現実には、多くの人が家族を持ち、住宅ローンを抱えながらもFIREを志しています。
つまり、「家を持つ=FIREを諦める」ではないということです。
では、住宅ローンとFIREはどのような条件なら両立できるのでしょうか。
「借金を抱えたまま自由になれるのか?」という矛盾に見えるテーマを、数字と価値観の両面から整理してみましょう。
FIREと住宅ローンが相性が悪いと言われる理由
FIREとは、株式や配当、投資信託などから得られる資産収入で生活費をまかなう生き方です。
そのため、理想形は「支出が少なく、資産収入で安定して生活できる状態」なのですが、ここに住宅ローンという固定支出が加わると、一気にバランスが崩れやすくなります。
たとえば、月10万円の住宅ローンを返済している場合、年間では120万円のキャッシュアウトになります。もし生活費が年間300万円なら、そのうちの4割がローン返済で占められる計算です。この時点で「生活費=資産からの取り崩し」モデルが成り立ちにくくなるわけです。
また、ローンを抱えたままFIREする場合、次のようなリスクも存在します。
- キャッシュフローの圧迫
運用収入が減ったり、配当が減配されると返済が滞る可能性がある - 逆資産状態のリスク
住宅の市場価値が下がると、ローン残高が資産を上回ることがある - 維持費の存在
固定資産税、修繕費、火災保険など、ローン以外にもコストが発生する
つまり、住宅ローンは「自由な支出設計を制限する要素」になりやすいのです。
このため、FIREを目指す人の多くが「ローンを抱えたままでは無理」と感じてしまいます。
しかし、それは単純な足し算・引き算の話に過ぎません。
次章では、ローンを返済しながらでもFIREを成立させるための現実的な条件を整理してみましょう。
両立の鍵は「キャッシュフローと現金バッファ」
キャッシュフロー
FIREの基本式はとてもシンプルで「資産からの年間収入>年間支出」となればOKです。
住宅ローンがある場合でも、この関係さえ維持できれば、理論上はFIREは成立します。
つまり問題は「ローンの有無」ではなく、「支出全体に対して資産収入がどれだけ上回るか」なのです。
ここで、具体的なシミュレーションを考えてみましょう。
- 年間生活費(住宅ローン含む):300万円
- そのうち住宅ローン返済:100万円
- 保有資産:5,000万円
- 運用利回り(取り崩し率):4%
この場合、資産から得られる年間収入は200万円(5,000万円×4%)です。
単純計算では、生活費に対して100万円が不足します。
しかし、その不足分を資産の取り崩しや配当、あるいは副収入や軽めの労働収入で補えれば、フルFIRE、サイドFIREとして成立します。
たとえば、在宅ワークやパートタイムで月8〜9万円稼げば、年間100万円を十分カバー可能です。
完全リタイアには届かなくても、「週に数日働きながら時間の自由を得る」生活は十分に現実的です。
FIRE後の住宅ローン返済に備える現金バッファ
FIREを目指す場合、住宅ローンを抱えながら資産運用を続けることになります。
このとき重要なのは、資産残高ではなく、月々の返済に必要なキャッシュフローから現金バッファを考えることです。
現金バッファの目安
現金バッファは次の式で考えるとわかりやすいです。
- 月々の返済額:ローンの毎月支払い額
- 想定耐久年数:株式市場の暴落時に耐えられる期間(目安3年)
- 金利上昇マージン:変動金利ローンの場合、金利上昇による追加支払い
なぜ「3年分」が目安か
過去の株価暴落(ITバブル、リーマンショック、コロナショック)を見ると、深刻な下落から回復するまでに3〜5年程度かかるケースが多いです。
暴落期間中に資産を取り崩さずローン返済を続けるには、最低でも3年分の返済資金を現金で確保しておくと安心かと思います。
金利上昇への備え
変動金利ローンでは、金利が上昇すると返済額も増えます。
例えば、金利が1%上がった場合、借入残高1,000万円で年間返済が約10万円増加します。
この追加負担も見越して、バッファに30〜60万円程度を上乗せすると、安心度がさらに高まります。
計算例
次の条件でどのくらいの現金バッファがあればいいか確認してみましょう。
- 月々の返済:8万円
- 想定耐久期間:3年
- 金利上昇マージン:50万円
現金バッファ = 8万円 × 12か月 × 3年 + 50万円 = 約340万円
この水準の現金があれば、株価暴落などの局面でも、少なくとも3年間は資産を売らずにローン返済を維持できます。
FIREを目指す人が選ぶ「住宅ローン戦略」の3パターン
住宅ローンを抱えながらFIREを目指す場合、すべての人に同じ正解はありません。
重要なのは、自分のキャッシュフローや価値観に合わせて「どのようにローンと付き合うか」を設計することです。
ここでは、FIRE志向の人が取りうる代表的な3つの戦略を紹介します。
パターン①:ローン完済後にFIREする
もっともリスクが少ないのが、このパターンです。
ローンをすべて返済してからFIREに移行すれば、住居費がほぼゼロになり、毎月の固定費が一気に下がります。
固定費が下がるということは、必要なFIRE資産額も小さくて済みます。
例えば、年間支出が300万円から200万円に下がれば、4%ルールで必要な資産は7,500万円→5,000万円に減ります。
この方法は、家族持ち・子育て世代にとっても安心感が高く、心理的にも安定しやすい点が特徴です。
唯一の難点は、「ローン返済中は働き続ける必要がある」という時間的制約ですが、リスクを最小化したFIRE戦略としては堅実です。
しかしながら、一般的に住宅ローンは数千万円もの負債であることが多く、その全てを返済してからFIREをするのは、あまり現実的ではないプランです。
パターン②:ローンを抱えたままFIREする
住宅ローンの金利が低く、返済額も軽めであれば、ローンを残したままFIREを実行する選択肢もあります。たとえば、ローン残高1,500万円、金利1%、月返済6万円程度であれば、資産からの収入だけで返済が十分可能です。
この場合、ローン金利が資産運用利回りより低ければ、むやみに繰上返済せず、低金利で借金を抱えながら運用を続ける方が資産形成上有利です。
ただし、注意点として、株式などの運用資産は短期的に大きく下落することがあります。セミリタイアした後にローン返済を資産から賄う場合、株価暴落時に資産を売却すると損失を確定させてしまうリスクがあります。
そこで重要なのが、さきほど説明した現金バッファの確保です。現金バッファを確保しておくことで、暴落時にも資産を売らずにローン返済を継続でき、心理的にも安心できるでしょう。
また、サイドFIREであれば副収入から住宅ローン返済に補填できるため、ローンを抱えたままのFIREは更に現実的なものとなります。
パターン③:家を資産とみなし、賃貸化・売却を前提にする
FIREを達成した後も、必ずしも「その家に住み続ける」必要はありません。
立地や物件の条件によっては、家を賃貸資産として運用する、あるいは売却して資金に変えるという選択肢もあります。
たとえば都市部のマンションであれば、FIRE後に地方へ移住して賃貸収入を得ることも可能です。
この場合、住宅は「負債」ではなく「キャッシュフローを生む資産」として機能します。
ただし、空室リスクや管理負担、税金などのコストも発生するため、事前に出口戦略を設計しておくことが不可欠です。
「住まいをどのように活かすか」をFIRE計画の一部として考えることが、柔軟なFIREの鍵になります。

いずれのパターンにも共通して言えるのは、「ローンがある=自由がない」とは限らないということです。重要なのは、ローンをどのように扱い、どの時点で“生活の自由度”を取り戻すかの設計です。
持ち家はFIRE後の安心にもなる
FIREを目指す人の中には、「借金を完全にゼロにして、身軽に生きたい」という人も多いでしょう。その発想は理解できます。
ただ一方で、FIRE後の生活の安定という観点から見ると、持ち家は大きな安心材料にもなり得ます。
まず、家賃が不要になるという点です。
FIRE後は収入の大半を資産運用に頼るため、毎月の固定費を減らせることは何よりも強みになります。住宅ローンを完済した持ち家なら、必要な生活費を大幅に抑えられる。これはFIRE後のキャッシュフローにおける「防御力」といえます。
さらに、家は「暮らしの拠点」という意味でも大きな価値を持ちます。
FIREを実現したあと、経済的な自由よりも、生活をどう安定させるかが重要だと考えています。家という自分や家族が落ち着ける場所があることで、日々の生活にリズムと安心感が生まれるのではないでしょうか。
また、将来的に働かない期間が長くなると、賃貸契約の審査が通りづらくなるという現実的な問題もあります。定職を離れた後の「住まいの確保」という観点からも、持ち家は一種のセーフティネットになります。
つまり、持ち家は「自由を制限する負債」ではなく、「安心を提供する資産」になり得るということです。FIRE後の生活において本当に大切なのは、資産額の大小ではなく、安心して暮らせる基盤を持てるかどうかです。
まとめ
住宅ローンとFIREは、一見すると相反するものに見えます。
「借金を抱えているのに自由を得るなんて矛盾している」と思う人も多いでしょう。
しかし実際には、ローンをどう扱うかによって、その意味は大きく変わります。
返済に追われて生活を制限されるローンは確かに自由を奪いますが、生活設計の中に織り込まれた「コントロールされたローン」は、FIREの道を閉ざすものではありません。
FIREとは、単に仕事を辞めることではなく、自分の人生を自分のペースで選べる状態をつくることだと思います。その意味では、家もローンも、自由を実現するための「道具」として考えましょう。

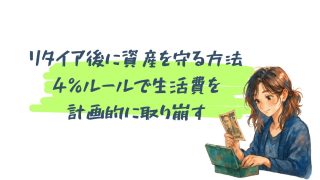


コメント