こんにちは、むーです。
突然ですが、皆さんは生活の中で、どんな税金を払っているか答えられますか?
給料から引かれるもの、スーパーでの買い物に上乗せされているもの、マイホームや車を持ったときに発生するもの…などなど、私たちの日常には思っている以上に多くの税金が関わっています。
私自身も、整理してみると「そういえばこれも税金だったな」と思うことが多々ありました。そこで、この記事では、自分の勉強の備忘録として「会社員が生活の中で考慮すべき税金」を整理してまとめました。ぜひ一緒に確認してみてください。
1. 給与や収入にかかる税金
所得税
所得税は、毎月の給料から支払う税金です。所得が多いほど税率が上がる「累進課税」で、5%から最大45%まで段階的に設定されています。ボーナスも含めて課税対象になるため、収入源が増えるとその分税金の負担も大きくなります。
| 課税所得の範囲 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~195万円 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 4,000万円超の課税所得に対して45% | 4,796,000円 |
所得税を下げる主な方法
所得税は「課税される所得」に対してかかるため、控除を活用すると負担を減らせます。会社員の場合は 年末調整 でほとんどの控除を申告できます。副業や医療費控除など年末調整で対応できないものは 確定申告 で申告します。
1. 控除を活用する
- 基礎控除
48万円(2025年現在何もしなくても勝手に控除されます。) - 配偶者控除・扶養控除
配偶者や家族がいる場合に控除される - 社会保険料控除
給与から差し引かれる健康保険や厚生年金など - 生命保険料控除・医療費控除・住宅ローン控除
支払った金額に応じて控除されます。
2. iDeCoやふるさと納税を活用する
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
掛金が全額所得控除の対象になり、節税効果が高いです。
- ふるさと納税
寄付額に応じて所得税・住民税が控除される仕組み。実質的に税金を減らせます。
住民税
住民税は前年の所得をもとに市区町村と都道府県に納める税金で、給与から毎月天引きされます(6月〜翌年5月)。
計算は「前年の給与 − 給与所得控除 − 各種控除(基礎控除・社会保険料控除など)」に標準税率10%をかけた金額が目安です。
例えば年収500万円の会社員なら、控除後の課税所得が約233万円として、年間の住民税は約23万円、月々約1万9千円が給与から差し引かれるイメージです。控除をもれなく申告することで課税所得を下げ、住民税も軽減できます。
| 項目 | 説明 | 標準税率(目安) |
|---|---|---|
| 市町村民税 | 市区町村に納める税金 | 6% |
| 都道府県民税 | 都道府県に納める税金 | 4% |
| 合計 | 給与天引きされる住民税 | 約10% |
※上記が全国標準ですが、特例や上乗せのある自治体もあります。
住民税を下げる方法
住民税も所得税と同じく課税所得が算定の基になります。給与から天引きされますが、所得税の控除が住民税にも反映されるので、控除を活用して住民税も減らしましょう!
社会保険料
会社員の給与からは、将来や万が一に備えるための保険料が自動的に差し引かれます。これを 社会保険 と呼びます。社会保険は、生活を守るために加入が義務付けられた公的な制度で、病気やケガ、失業など困難な状況に直面したときに給付を受けることができます。
主な種類と計算例
- 健康保険
被保険者や扶養家族の病気・ケガ・出産・死亡などに備える制度です。- 給与 × 健康保険料率(約5〜10%、会社と折半)
- 計算例:月収30万円 × 9.15% ÷ 2 ≒ 13,725円
- 厚生年金
老後の年金や障害・死亡時の年金・一時金を支給する制度です。- 給与 × 保険料率(18.3%、会社と折半)
- 計算例:月収30万円 × 18.3% ÷ 2 ≒ 27,450円
- 雇用保険
失業時の給付や教育訓練の支援など、労働者の生活・雇用の安定を目的とする制度です。- 給与 × 0.3〜0.6%程度
- 計算例:月収30万円 × 0.5% ≒ 1,500円
- 介護保険(40歳~64歳)
高齢者の介護サービスを支えるための制度で、40歳~64歳の健康保険加入者が支払います。介護保険料率は- 給与 × 介護保険料率 (1.64%、会社と折半)
- 計算例:月収30万円 × 1.64% ÷ 2 ≒ 2,460円
社会保険料を下げる方法
健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険は公的な強制加入制度で、給与に応じて料率が決まっています。そのため、社会保険料を自分の意思で下げることはできません。社会保険料は給与に比例して増えるため、給与が増えれば天引き額も増えます。
2.消費税など日常の税金
生活をする上で、日常の買い物やサービスでさまざまな税金を負担しています。消費税やたばこ税、酒税、ガソリン税など、支払うたびに上乗せされる形でかかりますが、普段はあまり意識せずに負担していることがほとんどです。
こうした税金は、支払いのたびに少しずつ負担していると覚えておくとわかりやすいでしょう。
| 税の種類 | 説明 | 税率・目安 |
|---|---|---|
| 消費税 | 商品やサービス購入時にかかる税金 | 基本10%、食品などは8%(軽減税率) |
| たばこ税 | タバコ購入時にかかる税金 | 商品価格に含まれる |
| 酒税 | 酒類購入時にかかる税金 | 商品価格に含まれる |
| ガソリン税・軽油引取税 | 燃料購入時にかかる税金 | リッターあたり課税(例:ガソリン53.8円/ℓ) |
| 宿泊税・入場料に含まれる税 | ホテル宿泊やレジャー施設利用時 | 地域や施設により異なる |
| 入湯税 | 温泉や銭湯などで課金される税金 | 1人1日あたり数十円~数百円(自治体による) |
3. 住まい関連の税金
家を所有したり購入したりすると、いくつかの税金がかかります。これらは住まいの所有や取得、所有に伴って発生する税金です。
- 固定資産税
土地や建物を所有しているだけで毎年課税されます。 - 都市計画税
都市計画区域内の土地・建物にかかる税金で、固定資産税と合わせて請求されることが多いです。 - 不動産取得税
土地や建物を購入したときに一度だけかかる税金です。 - 登録免許税
不動産の所有権や抵当権の登記をするときにかかる税金です。
4. 資産運用にかかる税金
株や投資信託、FX、仮想通貨などで得た利益にも税金がかかります。
- 国内株・投資信託の利益や配当金
- 原則として 20.315%の源泉分離課税 がかかります。
- NISA口座やiDeCoを活用すると、この源泉分離課税を 非課税 にできます。


- 米国株の配当金
- 米国で 10%の源泉徴収 が行われます。
- 日本でも課税されますが、確定申告で外国税額控除を申告することで 二重課税を回避 できます。
- 仮想通貨・FXの利益
- 雑所得として累進課税の対象となります。
5. ライフイベントで発生する税金
結婚・出産・相続など人生の節目でも税金がかかることがあります。
- 相続税:財産を相続したときにかかります。基礎控除があるため、一定額までは非課税です。
- 贈与税:年間110万円を超える贈与を受けた場合に課税されます。
まとめ
私たちの生活には、給与から天引きされる所得税・住民税・社会保険料から、日常の買い物やサービスで負担する消費税やたばこ税・入湯税、マイホームや車の所有に伴う固定資産税など、さらには資産運用やライフイベントで発生する税金まで、実にさまざまな税金が関わっています。

税金は、普段は意識せずに支払っていることも多いですが、種類や仕組みを知り、控除や制度を活用することで、手取りアップや資産形成に役立てることができるのではないでしょうか。
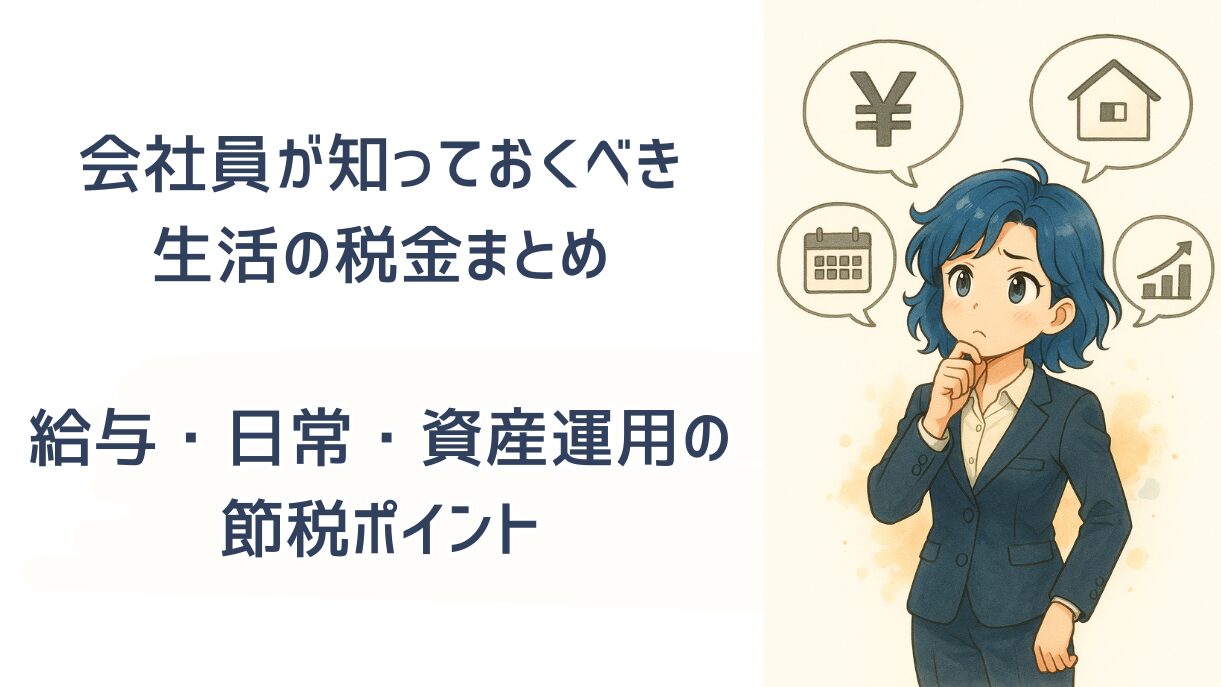


コメント