米国の長期金利が依然として高く、20年・30年国債の利回りはおよそ4.7〜5.0%前後です。この高利回り環境を背景に、米国国債への投資が再び注目を集めています。
中でも、東証で買える「20年超の米国長期国債ETF」は、円建てで手軽に購入でき、株式の下落局面ではヘッジ効果も期待できる存在です。
代表的な銘柄は、2255(iシェアーズ)・180A(グローバルX)・182A(MAXIS) の3本。いずれも「為替ヘッジなし」で同様の債券に投資しますが、信託報酬や分配金、課税制度(二重課税調整)の有無に違いがあります。
本記事では、3銘柄を比較し、最も合理的なETFを検証します。
3銘柄の基本情報比較
まずは、東証に上場している20年超米国国債ETFの基本情報を整理します。
いずれも為替ヘッジなしで、米国の長期国債指数に連動しますが、信託報酬・純資産総額・分配金利回りに差があります。
JPXより各ETFの2025年6月時点での情報を表にまとめました。
| 銘柄コード | 管理会社 | 信託報酬(税込) | 分配金利回り(年) | 純資産総額 | 対象指数 | 二重課税調整制度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2255 | ブラックロック | 0.154% | 約3.6% | 約53億円 | FTSE 米国債20年超セレクト・インデックス | 対象外 | 流動性が最も高い |
| 180A | グローバルX | 0.1045% | 約4.0% | 約9億円 | ICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Index | 対象 | 最低コスト、構成債券が最長 |
| 182A | 三菱UFJAM | 0.132% | 約3.2% | 約2億円 | ICE 米国債20年超指数 | 対象 | 純資産規模は小さい |
3銘柄はいずれも「20年以上の米国国債」に投資する点で共通していますが、運用会社・指数・コスト構造に明確な差があります。
- 2255(iシェアーズ) はブラックロックが運用し、純資産規模と売買流動性が圧倒的。信頼性と取引のしやすさを重視する場合に有利。
- 180A(グローバルX) は信託報酬が最も低く、構成債券の期間が25年以上とやや長いため、利回り水準も高め。長期保有コストを抑えたい投資家に向きます。
- 182A(MAXIS) は三菱UFJ系ブランドで安心感があるが、資産規模がまだ小さい。今後の成長次第。
二重課税調整制度の観点では、2255のみ対象外で、180Aと182Aは制度の適用を受けます(2025年9月18日更新版をJPX日本取引所HPにて確認)。
連動指数とETFの特性の関係
信託報酬
ETFの信託報酬は、主に運用会社のコストと指数の構成債券の管理コストに依存します。たとえば、180AのICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Indexは超長期債中心で構成されており、運用管理コストは低め(0.1045%)。一方、2255のFTSE米国債20年超セレクト・インデックスは債券の銘柄選定や再構成の頻度がやや高めで、信託報酬も0.154%とやや高くなります。
分配金利回り
指数に組み込まれる債券の残存期間が長いほど利回りは高めになる傾向があります。
180Aは25年以上の超長期債を中心にする指数に連動しているため、短期債より利回りが高くなります。182Aや2255は20年以上の長期債中心なので利回りはやや低めです。
値動き(価格変動リスク)
残存期間が長いほど、金利変動に対する価格感応度(デュレーション)が大きくなります。したがって、180Aの指数は超長期債中心で値動きが大きく、2255や182Aの指数は長期債中心で180Aより価格変動は穏やかです。
また、指数の銘柄選定の幅やリバランス頻度も価格変動に影響します。銘柄を限定して選定する指数は、特定債券の値動きに左右されやすくなります。
手数料で選ぶならどれ?
米国債ETFは、基本的に「値上がり益」よりも「利回り(インカム)」でリターンを得る資産です。そのため、信託報酬のわずかな差でも、長期ではリターンに確実な影響を及ぼします。
3銘柄の信託報酬(税込)は以下の通りです(2025年6月現在)。
- 180A(グローバルX):0.1045%
- 182A(MAXIS):0.132%
- 2255(iシェアーズ):0.154%
見た目の差は0.05%ほどですが、たとえば100万円を20年間保有した場合、単純計算で
- 0.10%:手数料合計 約2万円
- 0.15%:手数料合計 約3万円
と、1万円前後の差になります。金額としては小さく見えますが、再投資による複利効果を考慮すると、リターンの差はじわじわと広がります。
特に、長期債ETFのように利回りが3〜4%台で推移する資産では、0.05〜0.1%のコスト差は「リターンの1〜3%相当」に匹敵するケースもあります。

手数料を徹底的に抑えたいなら、180Aが最も合理的な選択肢と言えます。
分配金利回りの違い
3銘柄の中で最も高い分配金利回りを示しているのが 180A(グローバルX 超長期米国債ETF) です。2025年6月時点の想定分配金利回りは約 3.99%。一方、182Aは約3.2%、2255は約3.6%となっています。
この差の主因は、保有する債券の残存期間 にあります。
- 180A:25年以上の超長期米国債を中心に組み入れ
- 182A・2255:20年以上の長期米国債が中心
残存期間が長いほど利回りは高くなる傾向があるため、180Aの利回りが相対的に高くなっています。ただし、長期債は金利変動に対して価格のブレも大きくなるため、利回りが高い=価格変動リスクも大きい点には注意が必要です。

つまり、180Aは高利回りを狙う一方でリスクも大きめ、2255や182Aは利回りはやや低めですが、価格変動は比較的抑えられるETF、と整理できます。
騰落率からみる値動きの違い
東証上場の20年超米国債ETFは、株式下落局面でのヘッジ効果が期待されますが、短期的な金利変動や為替変動の影響で基準価額は上下します。
ここでは、2025年6月時点の騰落率(3か月・6か月・1年)を比較します。
| 銘柄コード | 3か月騰落率 | 6か月騰落率 | 1年騰落率 |
|---|---|---|---|
| 180A | -6.75% | -9.19% | -16.08% |
| 182A | -5.54% | -8.63% | -15.83% |
| 2255 | -6.52% | -8.61% | -15.46% |
180Aは25年以上の超長期債を中心に組成されており、短期的な価格変動は3銘柄の中で最も大きくなっています。182Aや2255はやや残存期間が短めの長期債が中心のため、値動きは180Aより穏やかで安定性が高い印象です。また、2255は純資産規模が大きく流動性が高いため売買の安定性に優れています。
短期的な基準価額の動きは、金利の上昇やドル円の変動によって影響を受けやすく、高利回りETFほどリスクも大きくなります。そのため、投資家は利回りの高さと価格変動リスクのバランスを踏まえ、保有目的やリスク許容度に応じて銘柄を選ぶことが重要です。
まとめ
長期投資でコスト最小化と分配金効率を最優先するなら、180Aが最も合理的な選択肢です。株価の急落リスクに備える目的で私も180Aを保有しています。
一方、流動性やブランド、安定性を重視する場合は2255や182Aも候補になります。
最終的には、自身の投資目的やリスク許容度に応じて、利回りと値動きのバランスを考慮しながら銘柄を選ぶことが重要です。

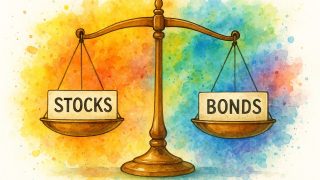


コメント