株式投資だけで資産を増やしている人は多いですが、将来使う予定のお金を運用している場合、株価の急落は無視できません。たとえば、リーマンショックのときには株式市場が暴落し、元の水準に戻るまで5〜6年もかかりました。このような大きな下落に直面すると、「このまま待つべきか」「資産を守る方法はないか」と不安になるものです。
そこで注目したいのが「債券」です。債券は株式より価格変動が小さく、暴落時には安全資産として買われるため、ポートフォリオ全体の下落幅を抑える働きがあります。実際、リーマンショック時にも債券は1〜2年で株式の下落分の半分以上を取り戻し、全体としては約2年半で元の水準に回復しました。
本記事では、債券投資のメリット・デメリットを整理し、どんな人が債券投資に向いているのか、逆に必要ないのかをわかりやすく解説します。将来の資金を安全に運用したい人にとって、参考になる内容です。
債券とは
債券とは、国や企業が資金を借りるときに発行する「借用証書」のような金融商品です。債券を買うということは、発行体にお金を貸すことを意味し、その見返りとして利子(クーポン)を受け取ることができます。満期が来れば、元本も返ってきます。
債券投資のメリット
値動きが安定している
株式と比べると価格変動が小さいです。債券の値動きが株より小さいのは、債券には「決まった利子がもらえること」と「満期になったら元のお金が返ってくること」がはじめから決まっているからです。
株は会社の業績や世の中のニュースで価格が大きく上下しますが、債券はあらかじめルールが決まっているので、価格が急に変わりにくく安定しています。特に国が発行する国債のように信用できる債券は、ほとんど安全だとみなされるため、さらに値動きが小さくなります。
定期的な利子がもらえる
債券の大きな特徴の一つは、「定期的に利子(クーポン)がもらえる」ことです。たとえば、額面10万円の債券で年利1%の利子がついていれば、1年間で1,000円の利子収入が得られます。
株式の場合は配当がある銘柄もありますが、業績次第で増えたり減ったりすることがあります。それに対して債券は、あらかじめ利率が決まっているため、毎年ほぼ確実に収入が入るのが安心ポイントです。将来の支出に備えて安定的な収入を作りたい人に向いています。
リスク分散になる
債券を組み込むもう一つの大きなメリットは「リスク分散」です。
株式だけで運用していると、株価が大きく下がったときに資産全体も大きく減ってしまいます。しかし、債券は値動きが比較的安定しているため、株式が暴落してもポートフォリオ全体の下落幅を抑えることができます。
たとえば、株式70%・債券30%で運用している場合、株式だけの運用より資産の上下変動が穏やかになり、精神的な負担も軽くなります。初心者や将来使うお金を運用する人にとって、安定性を高めるための重要な手段です。
債券投資のデメリット
リターンは株式より低い
メリットの裏返しにはなりますが、債券は値動きが安定している分、株式ほど大きな値上がりは期待できません。株式が急上昇した局面では、債券の存在がポートフォリオ全体の利益を抑えてしまうことがあります。
金利変動リスク
市場金利が上昇すると、既存の債券価格は下がる傾向があります。特に長期債を保有している場合、金利変動による価格の変動が無視できません。
デフォルト(債務不履行)リスク
企業や国が債務を返せなくなる可能性もゼロではありません。信用力の低い債券を買うと元本割れするリスクがあります。実際に、アルゼンチンは過去数十年の間に何度も国債のデフォルト(債務不履行)を起こしています。
債券投資に向く人、向かない人
債券をポートフォリオに組み込むなら何%?
債券の割合は、一人ひとりの年齢やリスク許容度、そしてお金を使うタイミングによって変わってきます。ここでは、初心者でもイメージしやすい代表的な目安をご紹介します。
よく使われるのが「100 − 年齢」で株式の割合を決める方法です。残りの部分が債券の割合になります。
例えば…
- 30歳なら株式70%、債券30%
- 60歳なら株式40%、債券60%
年齢が上がるにつれて、株式のように値動きの大きい資産よりも、債券のように安定した資産の割合を増やすことで、資産全体のリスクを抑えることができます。つまり、無理なく資産を守りながら運用するイメージですね。
もちろん年齢だけで決める必要はありません。自分がどれくらいリスクを取れるかによっても調整が可能です。リスクをあまり取りたくない人は債券の割合を多めに、少しくらい下落しても大丈夫という人は株式の割合を多めに、といったイメージです。
500万円を投資した場合のリーマンショック時シミュレーション
仮に500万円を投資した状態でリーマンショックを迎えた場合のシミュレーションをしてみました。株式のみと債券を組み込んだ場合で比較します。
| 運用スタイル | 株式割合 | 債券割合 | 投資額 | 下落時の評価額 | 回復時の評価額 | 下落幅 | 回復までの期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式のみ | 100% | 0% | 500万円 | 250万円 | 500万円 | -50% | 約4年 |
| 株式70%+債券30% | 70% | 30% | 500万円 | 325万円 | 500万円 | -35% | 約2年6ヶ月 |
| 株式50%+債券50% | 50% | 50% | 500万円 | 375万円 | 500万円 | -25% | 約2年 |
株式だけで運用していた場合、リーマンショックで評価額は半分の250万円まで下がり、元の500万円に戻るには約4年かかりました。下落幅が大きく、回復にも時間がかかるため、将来使う予定のお金を運用する場合には大きなリスクとなります。
一方で、株式70%、債券30%に分散して投資していた場合、下落時の評価額は325万円まで抑えられ、元に戻るまでの期間も約2年6か月と短縮されました。さらに株式50%、債券50%にすると、下落幅はさらに小さくなり評価額は375万円までで、回復も約2年で完了します。
このように債券を組み込むことで、株式だけの投資に比べて下落のダメージを和らげ、回復期間を短くすることが可能です。特に、将来使う予定のあるお金を運用している場合は、単にリターンを追い求めるよりも、こうした安定性を意識したポートフォリオ設計が重要になります。
筆者の考えは?
私の考えでは、資産形成の初期段階では、株式中心で資産を成長させつつ、現金もある程度確保しておくシンプルなスタイルが基本だと思っています。リターン重視で成長を優先しつつ、暴落時に株を仕込めるだけの現金を持っておくことで、暴落時の心理的負担も和らげられます。
一方で、FIRE(経済的自立・早期リタイア)の目標金額に近づいたり、実際に資産を取り崩す年齢が見えてきた段階では、債券の組み入れを検討しても良いと考えます。債券を一定割合組み込むことで、株式だけの運用に比べて下落リスクを抑え、取り崩す際の資産の安定性を高められるからです。
つまり、資産形成期は「成長重視」、取り崩し期や目標金額に近づいた段階では「安定重視」にシフトしていくイメージで、株式と債券をバランスさせるのが理想的だと考えます。
まとめ
債券は株式に比べて値動きが安定し、定期的な利子収入が得られるため、将来使う予定のあるお金を運用する人にとって資産の下落リスクを抑える有力な手段です。
資産形成の初期は株式中心で成長を重視しつつ、現金を確保して暴落に備え、FIREや資産取り崩し期に近づいたら債券を組み入れて安定性を高める。このようにライフステージやリスク許容度に応じて株式と債券をバランスさせることが、長期的に安心して資産を運用するポイントです。
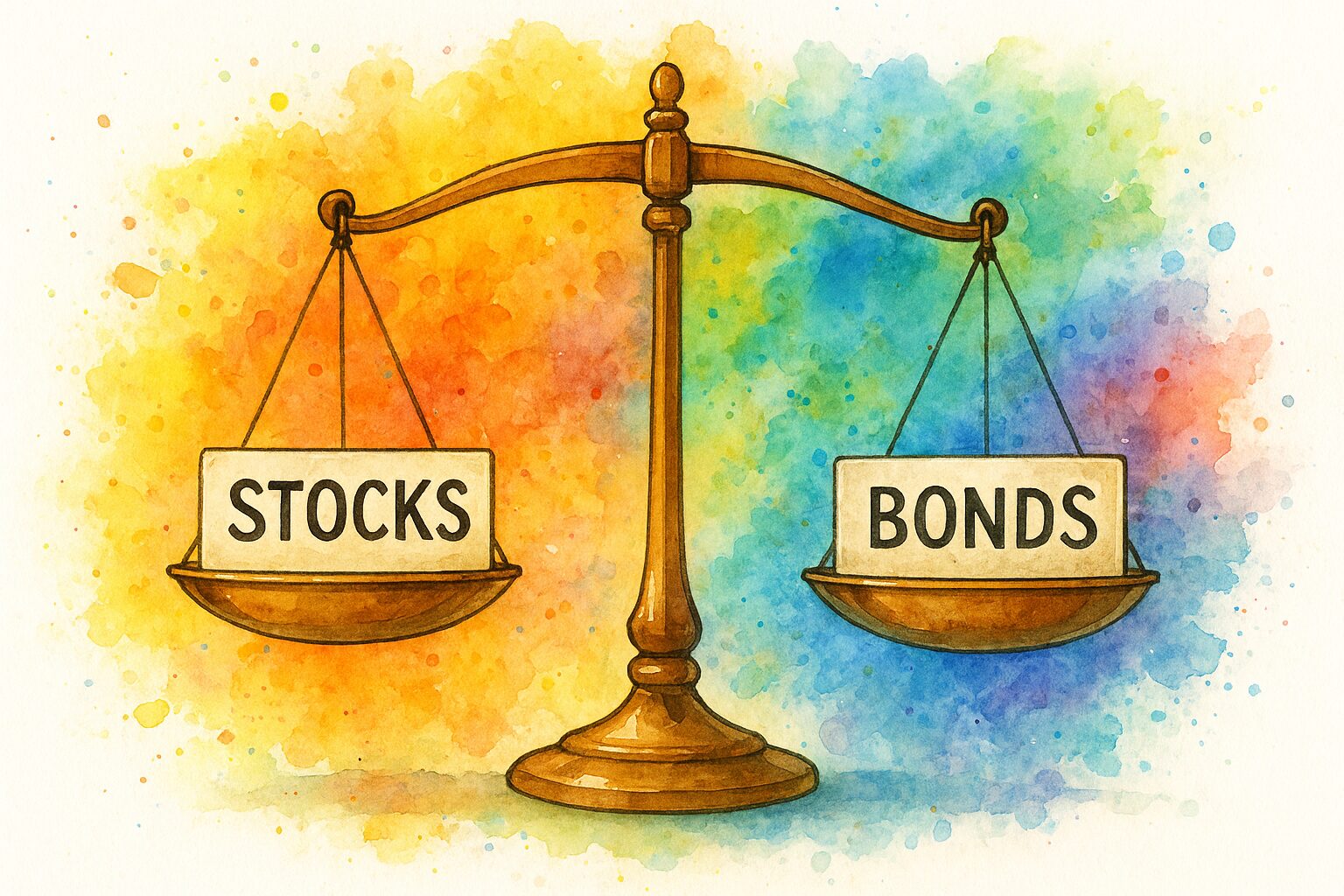




コメント